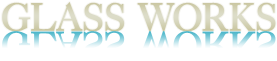本郷小学校ではもう何十年も立場川の清掃を年1回続けている。ワタクシが漁協専務理事の時には県に申請して表彰状を贈ったりもしている。また校舎の前にはせせらぎが流れているのだが、最近は土砂が堆積していて「せせらぎ」とはとても言えない状況になっている。で、2年生が中心となってこの「せせらぎ」の土砂を何日もスコップですくって少しでも綺麗にと取り組んでいるのだが、到底子供達の手には負えない量である。ただ、この作業で「ドジョウ」を何匹か捕獲し、教室の水槽で飼っていたりする。
で、先月にはワタクシが提案して消防団に出て貰い、ポンプ車で土砂を洗ってもらった。こういう所は田舎の小学校の良いところで、親も殆どが卒業生であるし、消防団員だったりする。
7月に2年生のクラスで立場川に棲む「渓魚」について話をしたのだが、その折、子供たちから「川の魚を取って来て、「せせらぎ」で飼ってみたい」という話があった。イワナやアナゴは水温が高くて到底「せせらぎ」では飼えないが、「アブラッパヤ」ならひょっとすると生きられるかもしれないと話し、ではアブラッパヤはどうやったら捕まえられるとの事で、「魚トラップ」の作り方を説明したのである。ワタクシが子供の頃には「セルビン」といってセルロイドで出来たトラップを売っており、多摩川などで散々ハヤを獲ったものである。現在ではペットボトルを使ってのトラップの作り方がネットに出ている。その話を担任のホシノ先生にも話したところ、各自が1個づつ作ったとの事で、昨日は実際に立場川に仕掛ける事となったのである。
昨日は朝8時半に2年生のクラスに行き、ちょっと仕掛け方を話した後、外で魚肉ソーセージを石で細かくし、ワタクシが持参した「さなぎ粉」を練り込んで、いざ立場川へ。担任と副担任、補助教師2名の4人の先生とワタクシで歩いて15分ほどの立場川へ31名の小学2年生を連れて行くというのはそれだけでなかなかに大変な事である。
県道下で入渓し易い場所から川に降り、各自思い思いの場所にトラップを仕掛けるのだが、説明した通りに直ぐに流れの緩い場所に仕掛ける子供は良いのだが、流れの早い場所に入れて流されたり、川の中をトラップを引きずって歩く子、プールさながらに服に長靴で半分泳ぐ子と、机に座っての授業から解放された喜び?で大はしゃぎである。
30〜40分掛けてまあそれぞれの場所に設置し終えた後、また今度は登りとなる学校へ3時間目が始まる前には戻る。
まあ、ヒナの群れである。小学校の先生というのはかくも大変な職業かと改めて感じる。
それにしても子供の足で歩いて10数分でイワナやアマゴが棲む川に行ける環境というのは素晴らしい事である。また担任のホシノ先生という若い女性教師が、子供達の興味や要望を一生懸命実現しようとしてくれている姿にも感動した。管理教育が田舎とはいえ行き届いた中で、実際に泥まみれになって「せせらぎ」を何日も掃除し、30名もの「ヒナ」を川まで連れて行き、子供達の手で実際に魚を獲らせるというのは熱意が無ければとても出来ない事であり、本当に頭の下がる思いであった。
今日はまた朝から子供達を引き連れてトラップの回収に行ったはずである。ワタクシは生憎病院の予約が入っていて行けないのだが、24時間もトラップを置きっぱなしで果たして魚が入っているか少々心配である。
これを書いている途中で担任のホシノ先生から今日の成果についての報告の電話があった。クラス全員で締めて41匹を捕まえた由。ワタクシの仕掛けたトラップには14匹が入っていたそうな。全部バケツリレーで学校へ持ち帰り、3つの水槽に入れたとの事であった。ヤレヤレ、24時間もトラップを入れておいたので心配であったが、ほっとした。
また全く入っていないトラップもあり、どうしても獲ってみたいとの子供隊の要望を受け、16日に再度行いたいとの事で
出来れば再度同行して欲しいとの事。「ではさなぎ粉を用意して伺う」と返事。また来週には富士見高校生が「せせらぎ」の上流にある調整用の小さな池の泥上げを手伝ってくれる事になった由。
子供達にとっては貴重な経験であるし、将来的に川を守ることに繋がると思い行ったものである。
(尚、川でのトラップに関しては大部分の河川で禁止されているのだが、釜無川漁協では対象魚をイワナ・アマゴ・ニジマス
としているので、ここは小学生の教育活動の一環として漁協でも大目に見てもらっている。また禁止されている漁法や禁漁期間等に関してもきちんと教えた上で行っている)