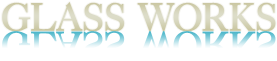朝から快晴でぽかぽかと暖かい。ここ一週間近く土踏まずの生活をしていたのだが、禁断の煙が切れ町に買いに下りる。コブシは既に花を落とし、桜もそろそろ散り始めているが、唐松の新緑が随分と進んでいる。
帰って庭を巡視。ナニ、巡視といってもワタクシにとっては自然栽培の食物が勝手に育っているか見て回るのである。アチャ、タラの芽が大きくなり過ぎている。 13〜14個採る。ま、天ぷらにするならこのくらい大きい方が美味い。ワサビも全て真っ白な可憐な花を咲かせている。食べごろである。
13〜14個採る。ま、天ぷらにするならこのくらい大きい方が美味い。ワサビも全て真っ白な可憐な花を咲かせている。食べごろである。 ウドも大分成長したが、これはもっと大きくして、新芽を増やしてから採れば当分は天ぷらを食べられる。
ウドも大分成長したが、これはもっと大きくして、新芽を増やしてから採れば当分は天ぷらを食べられる。 セリはそろそろ終盤である。水の中で育ったセリより、周りの雑草の中で育ったセリは茎の部分が長くて柔らかい。二掴みほど採る。
セリはそろそろ終盤である。水の中で育ったセリより、周りの雑草の中で育ったセリは茎の部分が長くて柔らかい。二掴みほど採る。
正に『山笑う』である。庭だけではなくちょっと登れば色々な山菜が採れる時期であるが、まだまだ土踏まずを続けなければならない。困ったことである!